| . |
古橋悌二『memorandum』
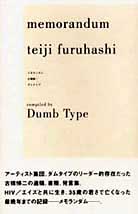 |
|
古橋悌二
『memorandum』
リトル・モア、2000
|
|
1995年10月29日――この日付を鮮明に覚えている者は少なくないだろう。そう、きしくもこの日、ダムタイプの中心メンバーであった古橋悌二が、AIDSによる敗血症のため35歳の若さで夭逝した。その若すぎる死が大々的に報道され、各方面から惜しまれたことは未だ記憶に新しい。そういう次第なので、昨年11月の末に古橋の遺稿や書簡、発言の記録や関係者の追悼文などがまとめられた本書『memorandum』(ちなみにこのタイトルは、古橋亡き後も精力的に活動を続けるダムタイプの最新作と同名だ!)を書店の店頭で目にした際、真っ先に評者の頭をよぎったのは「あれからもう5年も経ったのか!」という思いであった。
その一方で、本書を一読した後に思うのは、古橋の生きた密度の濃い時間のことである。ダムタイプが結成されたのは1984年なので、古橋のアーティストとしての活動期間は実質10年程度に過ぎない(しかも、評者がその作品を実見しえたのはそのうちほんの数年に限られる)のだが、その短期間のうちに古橋/ダムタイプは、テクノロジー社会の疎外感を舞台化した《pH》や自らのHIV感染を主要なモチヴェーションとする《S/N》、さらには「愛」のメッセージをワーク・イン・プログレスの手法で映像化したソロ・ビデオ・パフォーマンス《LOVERS》など、独特の手法と世界観に基づく意欲作を矢継ぎ早に発表し続けた。本書に散りばめられた様々な断章は、単に故人を偲ばせるばかりでなく、マルチメディア・パフォーマンスとでも呼ぶべき表現形態の確立や、HIV+のカミングアウトに伴うポリティカル・アイデンティティの導入など、古橋/ダムタイプが現代のアートに対して提起した問題の重要さをもあらためて考えさせる契機に満ちている。評者はただ一度、生前の古橋の肉声に接する幸運に恵まれたことがあり、本書の諸々の断片から彼特有の軽妙な語り口を思い出さないわけではないが、しかし本書の提起する「memorandum」とは、むしろ一般に広く共有されるべき記憶を指していると言った方が適切であろう。
森村泰昌『空想主義的芸術家宣言』
 |
|
森村泰昌
『空想主義的芸術家宣言』
岩波書店、2000
|
|
周知のように、ダムタイプはもともと京都芸術大学の学生たちによって結成されたパフォーマンス・グループである。
古橋もまた、結成当時は同校の構想設計専攻に在籍する学生だったわけだが、実は当時同専攻で、やはり同校出身のアーティスト・森村泰昌が写真の授業を担当していたという事実には何らかの因果関係が認められるのだろうか? 古橋と森村――確かに、この二人の名を並べて語ることには避けがたい違和感が付きまとう。独特のメディア・パフォーマンスによって国際的な名声を確立した半面 、その根底にはどこか京都的な土着性を感じさせる点では共通しているものの、その作品の意図や効果は全くの別物なのだから。別段師弟関係らしきものも存在しなかったようだし、ただ80年代の一時期に同じ大学のキャンパスですれ違っていたであろう関係だけを梃子に両者の接点を語るのには、明らかに無理があるだろう。だが、やはり11月末に刊行された森村の新著『空想主義的芸術家宣言』は、その明らかな無理を冒してみたいという欲望を引き起こす厄介な書物でもある。
これまた周知のように、森村はセルフ・ポートレートに拘りつづけている作家である。おのれの華奢な肉体を華美なメイクや衣装で飾り立てて、時には映画女優に、時には名画の登場人物に扮して、細心の注意を払って徹底的にキャラクターを作り込んでいく。もちろん、その「美しさ」は万人受けからは程遠い毒気を孕んだものであり、森村のコスプレが徹底していればいるほど、逆にその似姿を「滑稽」とか「醜悪」と感じてしまう観客の嫌悪を増幅する逆説もまた否定しがたい。一貫してダムタイプを擁護してきた半面、森村を「吉本的」と揶揄した浅田彰の批判などは、そうした否定的な価値判断の典型であろう(そして、以下に検討するようにこの指摘は圧倒的に「正しい」のだ)。
ところが、本書を一読した後では、この「吉本的」という揶揄ですらどことなく肯定的なニュアンスへと変質してしまう。タイトルが示す通り、本書は「空想」をキーワードとした森村の芸術観が述べられた書物であるのだが、森村は自分の作品が宝塚や吉本興業といった関西土着のサブカルチャーから強く触発されていることを率直に告白し、それを彼特有の美術史理解と絡めて展開して、一連のポートレート作品に至った経緯を説得力豊かに語ってみせている。実のところ、国際的な名声を獲得した現時点でさえ、森村のポートレート作品には、果たしてシンディ・シャーマンのような類例と比較検討されてその真価が問われるべきなのか、あるいはオリエンタリズムにおもねる代物なのか、未だに評価の定まらない要素が残されており、その点でもっぱらコスモポリタニズムの地平で作品が評価されてきた古橋/ダムタイプとは明らかに位相が異なっている。あるいは、両者を最も隔てているのはこの位相の差異なのかもしれない。
Michael Rush『New Media in Late 20th-Century Art』
 |
|
Michael Rush
New Media in Late 20th-Century Art,
Thames & Hudson, 1999
|
|
そして、この全く異質な両者の並列は、その共通項でもあるアートとメディアの戦略的な関係の検討を否応なしに迫ることになるだろう。だが、残念なことに、メディアアートへの関心に然るべき道筋を与えてくれる日本語の入門書・概説書となるとほとんど存在しないのが実情である。そこでここでは、その遺漏を補う洋書として、Michael Rush 『New Media in Late 20th-Century Art』を挙げておきたい。同書は、Thames&Hudsonの美術入門叢書のラインナップを為す一冊であり、20世紀美術におけるメディアの役割が、マレーやマイブリッジの連続写真から近年のWebアートに至るまで、クロノロジーに忠実な記述でコンパクトにまとめられている(ちなみに、同書では《LOVERS》の分析も為されているほか、日本の他のメディアアートへの言及も散見される)。実験映像寄りの話題が多くを占める作家作品選択の恣意性や、概説書にありがちなフラットな記述が気にならなくはないが、少なくとも既存の日本語類書にはない包括的な視点が認められることは確かだし、このような良質な概説書が訳出されてもよいのではないか、と評者は考えている。容易に入手可能で、また英文も平明な書物なので、是非とも読者各位が本書を手にとり、その当否を判断してもらいたいものである。
関連文献
Yukiko Shikata "WHITE OUT: Dumb Type's Image Machine" in Art AsiaPacific vol.27, 2000
浅田彰「21世紀のパフォーミング・アート」、『Voice』2001年1月号
森村泰昌『踏み外す美術史』、講談社現代新書、1998
『森村泰昌――美に至る病/女優になった私』展カタログ、横浜美術館、1996
伊藤俊治『電子美術論』、NTT出版、1999
マヌエル・デ・ランダ『機械たちの戦争』杉田敦訳、アスキー出版局、1997
|
|