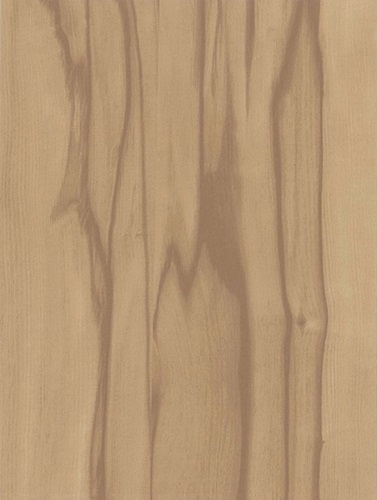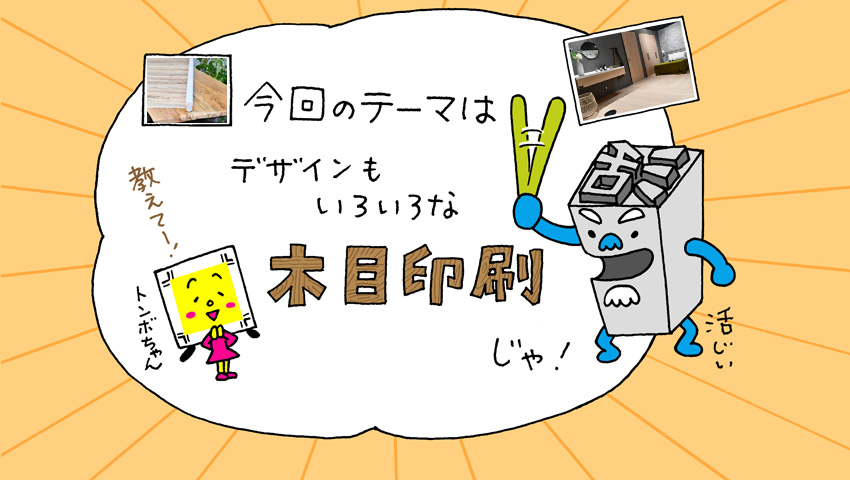木にも石にも水にもなれる建材「アートテック」の可能性を専門家と深掘り!
- X(旧Twitter)にポスト(別ウインドウで開く)
- メール
- URLをコピー
- 印刷
DNPが開発したアルミ外壁パネル「アートテック」。さまざまなデザインをオーダーメイドで印刷できるだけでなく、アルミならではの軽量性や高い耐候性などのメリットを併せ持っています。そんなアートテックが建築設計に果たす意味とは? そして、アートテックは建築家のクリエイティビティをどう解き放つのか? 建築系Webメディア「アーキテクチャーフォト」の編集長・後藤連平さんと、開発やデザインに携わるDNPのメンバーが、未来の建築物のデザインを思い描けるような“ワクワク”が盛りだくさんの座談会を実施しました。
目次
- 「手作業」から「既製品」へ。建材の移り変わり
- 遠くから見ても「木」と認識されるための印刷技術
- 石にも金属にも、水にもなれる
- 手作業を「凌駕する」カスタマイズ性。アートテックは建築家の創造力を解き放つ!
|
|
【プロフィール】(写真右から)
後藤連平(ごとう れんぺい)さん
1979年、静岡県磐田市生まれ。2002年京都工芸繊維大学卒業、2004年同大学大学院修了。組織設計事務所と小規模設計事務所で実務を経験した後に、アーキテクチャーフォト株式会社を設立。22年にわたり建築情報の発信を続けており、現在は、建築と社会の関係を視覚化するWebメディア「アーキテクチャーフォト」の運営をメインに活動。著書に『建築家のためのウェブ発信講義』(学芸出版社)など。
江川悠起(えがわ ゆうき)
大日本印刷株式会社 生活空間事業部 総合企画営業本部。アートテックの営業を担当。
司馬慧理(しま えり)
大日本印刷株式会社 生活空間事業部 総合企画営業本部。アートテックにまつわる営業活動をサポート。
中村日向子(なかむら ひなこ)
大日本印刷株式会社 生活空間事業部 イノベーティブデザインセンター。アートテックのデザインを担当。
中井康介(なかい こうすけ)
株式会社DNPエリオ 技術部。アートテックの開発を担当。
「手作業」から「既製品」へ。建材の移り変わり
——本日のテーマは「建材」です。建築物にとって建材は欠かせませんが、建築家の皆さんは建材をどう捉えているのでしょうか?
後藤連平さん:以前、著名な建築家の事務所では、「設計する際に、まずは世界中から建材を探す」と聞いたことがあります。建築家が建物のデザインを考えるうえで、建材はそれくらい大切な要素ということですね。
そして、「探す」という言葉が表すように、現代の建築現場で使われる建材は主に「既製品」です。
私はかつて古い木造住宅の耐震診断に携わっていたのですが、たとえば昭和40年代から50年代頃に竣工した建物には、職人さんが手作業でつくったところが今よりもたくさん存在していました。
——「手作業」のところが多いとはどういうことでしょうか?
後藤さん:たとえば、土壁も多かったですし、仕上げとしてモルタル*1や漆喰のような左官材もよく用いられていて、職人さんが手作業で塗っていました。しかし今では、外壁には、「サイディング」と呼ばれるパネルを壁に装着する方法が大多数になっています。設置は職人さんが行いますが、既製品を活用することで工期が短縮できる、耐久性も上がるなど、社会のニーズに応えられているのだと思います。
- *1 モルタル:セメントと砂と水を混ぜてつくる建材
|
サイディングの外壁の例 |
一方で、建物が既製品ばかりでつくられるようになると、建築家がデザインや設計にオリジナリティを出しにくくなるという側面もあります。おそらく多くの建築家が、「ゼロから自分の構想の下に創造したい」と考えているのではないでしょうか。ですが、予算などの条件もあり、そう簡単なことではありません。
手作業から既製品へと時代の流れが移り変わるなか、どのようにオリジナリティを打ち出すか、あるいは独自性を発揮できるような建材をいかに見い出すかということは、現代の建築家にとって必要なスキルになっていると言っていいと思います。
遠くから見ても「木」と認識されるための印刷技術
——そんなテーマに対して、アートテックという建材がどうアプローチできるのかを掘り下げていきたいです。DNPはそもそもアートテックをどのような経緯で開発したのでしょうか。
中井康介:25年ほど前、上海の「万都中心大厦」というビルの外壁にアルミパネルを使いたいとのオーダーがあり、それにお応えして提案したのが外装材としてのアートテックの始まりです。ただ、当時はまだ、商品として広く展開していたわけではありませんでした。
|
アートテックが使われた上海の万都中心大厦(1999年施工) |
一方で開発当初から耐候性は十分だったので、万都中心大厦への採用がプラスに働き、2010年頃から国内の建築物に使われることが増えました。2014年からは北米の建築物への採用が進み、デザインバリエーションの増加、設備増強もあわせて行っていきました。
江川悠起:現在のアートテックは、屋外環境での経年劣化要因を人工的に再現し商品の寿命を予測する「促進耐候性試験」において、少なくとも20年間は劣化しないという評価を得ています。上海の万都中心大厦でも、依然としてほぼ劣化のない状態で使用されています。
——物件への初採用から約25年の間に、どのように建築現場に浸透していったのでしょうか。
中井:兼ねてから「耐久性の高い木材を使いたい」というニーズをお持ちだった隈研吾さんに、2013年、玉川高島屋(東京都世田谷区)のリニューアルで採用いただき、それがきっかけで少しずつ認知されてきた印象です。もちろん、まだまだ知られていない建材ではありますが……。
司馬慧理:木を大胆にあしらう隈さんの建築と、デザインの自由度と耐久性の高さを兼ね備えたアートテックの相性が良かったのかもしれません。
|
DNP・司馬慧理 |
たとえば、フォレストゲート代官山(東京都渋谷区)は木箱を積み重ねたようなデザインが特徴的で、外装に木目柄のアートテックを使用しています。
|
フォレストゲート代官山(2023年施工) |
後藤さん:アートテックの公式サイトに掲載されている隈研吾さんへのインタビュー*2を読んで、面白いなと思ったのが、より「木らしく」感じるように木目柄の大きさや色の濃淡を操作しているということ。このアートテックの木目柄は、遠くから見てもしっかり木目が認識されるように、木目柄を拡大しているそうですね。
-
*2 2021年8月インタビュー「Kengo Kuma and Associates - 隈研吾建築都市設計事務所様
隈研吾からみたアートテック®の可能性と建築の未来」
https://www.dnp.co.jp/biz/case/detail/20173079_4968.html
|
フォレストゲート代官山に使われているアートテックの木目柄 |
中村日向子:はい。本物の木と同じサイズの模様だと、道路をはさんで眺めたとき、単なるベージュ色の壁に見えてしまうんです。その点、フォレストゲート代官山の外壁デザインは、「印刷物だから模様の縮尺も自由に変えられる」というアートテックのメリットが存分に生かされているように思います。
|
フォレストゲート代官山に使われているアートテック |
後藤さん:なるほど、だから意図的に木目を強調しているのですね。これは、木の再現から出発して、何か別の可能性を切り拓いているようにも思えます。
司馬:デザインの可能性を広げる、という側面だと、徳洲会ジムナスティクスアリーナ(神奈川県鎌倉市)も当てはまりそうです。ルーバー*3に木目調のアートテックが使われているのですが、かなりシャープな形状のため、本物の木ではつくれなかったそうです。
- *3 ルーバー:幅の狭い羽根板を一定間隔で縦や横に並べたもの。主にドアや窓に使われる。
|
徳洲会ジムナスティクスアリーナ(2024年施工) |
石にも金属にも水にもなれる
——アートテックは木の風合いを生かしたデザインに使われることが多いのですか?
中村:木以外をモチーフにしたデザインをオーダーいただくことも少なくありません。たとえば百貨店や銀行のような建築物では、重厚なイメージをつくるために石を活用するのですが、建物の下部は本物の石を使えても、3階や4階といった上部は安全性と重量の観点で石が使えないんです。そこで、下部に使用している石と同じ質感や風合いを再現でき、軽量で高所施工にも適しているアートテックを使って違和感なく仕上げます。
|
石を模したアートテックを活用した長谷工南砂町駅前ビル(東京都江東区、2018年施工) |
加えて、アートテックなら「石のようで石でない」雰囲気をつくることもできます。「素地生かし」といって、素地であるアルミらしさを残したまま表面にデザインを印刷する技術を活用します。こうすると、見た目は石なのに質感は金属という不思議な雰囲気に仕上げられるんです。
|
グラニット(御影石)を表現したアートテック |
中井:自然界では偶然生み出される柄を意図的につくり出せるのもアートテックの強みです。たとえば、リン酸で処理*4をしたときに金属の表面に生じる「リン酸柄」。
- *4 リン酸処理:金属の耐食性を高めるメッキ処理のひとつ
|
リン酸柄を表現したアートテック |
中村:リン酸柄は「見た目がきれい」なので、さまざまな商品の意匠としても活用しているのですが、自然発生する柄なのでデザインをコントロールするのが非常に難しくて……。
——どんな模様になるか、やってみないとわからないということですね。
中村:はい。その点、アートテックなら印刷ですから、理想的なリン酸柄をつくれますし、色合いも調整できます。リン酸柄は本来ダークグレーの色合いになるのですが、明るいシルバーや、逆にもっと暗いブラックにも仕上げられるんです。ローズゴールドでつくったこともあるんですよ。
|
ローズゴールドのリン酸柄 |
司馬:ローズゴールドのリン酸柄に光が当たると、とても美しいんです。
中井:ローズゴールドのリン酸柄アートテックはヒューリック錦糸町コラボツリー(東京都墨田区)に採用されています。太陽光の角度で色が変化するため、時間帯によって見え方が変わるというユニークな設計です。
|
ヒューリック錦糸町コラボツリー(2023年施工) |
後藤さん:偶然生み出される柄を意図的につくり出せるなら、経年変化のような表現もできるということでしょうか。建築家の多くは、木のような自然素材が変化していく過程に「美」を見出すように思います。
中井:たしかに「経年の雰囲気」をご希望されるお客様もいらっしゃいますね。20年くらい経過した風合いにしたい、とか。
中村:実は、錆を表現したアートテックも存在します。本物の錆は光らないのですが、「光沢のある錆」にも仕上げられるので、建築物にも活用しやすいように思います。
|
光沢のある錆を表現したアートテック |
後藤さん:面白いですね。もちろん、本物の素材が持つ固有性に価値があるのが前提となりますが、その再現を起点として、さまざまなカスタマイズができる技術や可能性があるというのは興味深いところだと思います。
司馬:従来の建材では実現しにくい表現という点では、新綱島駅(東急新横浜線)の対向壁もユニークです。駅のある綱島(横浜市港北区)は鶴見川の流れる「川の町」ということで、駅のホームのデザインテーマが「水」でした。そこで、水の雰囲気をつくり出すため、さざ波をイメージしたブルー系のスクエア柄をあしらいました。こうしたデザインが建材として表現できるのも、アートテックならでは!です。
|
新綱島駅の対向壁(2022年施工) |
——水のような、本来建材になり得ないものを建材として表現するのは、とてもクリエイティブですね。
中村:観光地などからは特に、町のシンボルを建築物に組み込みたいというオーダーをいただくことが多いので、たとえば川や森をモチーフにしたいというご要望にどう応えるか、工夫のしがいがあります。
——でも、柔軟性が高いと、発注者のオーダーに柔軟に応えなければいけなくなると思います。デザインや開発の際の苦労も多いのでは?
中村:そうですね。細かなオーダーに応じてサンプルを何回もつくって提案することもありますし、工場に足を運んで「もうちょっと赤くなりませんか?」と直接交渉することもあります(笑)。
そして、あらゆるオーダーに応えられるようにするため、オーダーがなくても日頃から絵柄のストックをつくっていて、そのパターンはすでに1万を超えているかもしれません。
|
DNP・中村日向子 |
中井:開発側としても、どんなオーダーにも応えられるよう、これまで開発してきた仕様の掛け合わせでなんとかならないか、スペックとして実現できないか、柔軟に検討しています。
|
DNP・中井康介 |
江川:基本的なスペックは前提にありますが、もともとアートテックのデザインなどは物件ごとにカスタマイズして提案しています。もちろん、過去に使用したデザインをそのまま使うこともできますが、それをベースに色を変えたり、模様の強弱をコントロールしたりといったアレンジもできます。ロット制限もかけていないので、少量でも対応できるのが強みですね。
|
アートテックのサンプルを手に取る後藤さん。「色や柄は同じでも、艶感が違うだけで大きく印象が変わりますね。」 |
手作業を「凌駕する」カスタマイズ性。アートテックは建築家の創造力を解き放つ!
——ここまでアートテックのさまざまなメリットを見てきました。アートテックはまだまだ新しい建材ですが、建築業界は今、この製品をどのように受け止めていますか?
江川:建築家の方は、建材についてはやはり「本物を使いたい」と考えるものです。そのため、もともとアートテックに興味を持っていた方は別として、初めて知る建築家の方にアートテックを提案すると、「それってフェイクってことですよね」とおっしゃることが多いですね。そこから始まり、単なるフェイクではなく、アートテックだからこそできることもある!というメリットをご説明しています。
|
DNP・江川悠起 |
後藤さん:たしかにフェイク、つまり自然素材の色や模様を“再現”できるのもアートテックの特徴ですよね。ただ、それ以上に、アイデアを飛躍させてオリジナルの柄などで“固有の価値を生み出せる”ことこそがアートテックの真価だと、今日お話を聞いて思いました。
今後アートテックを広めていくには、その点をもっと強調したほうがいいと思います。というのも、本物の木がそこにあるなら木を使いたいという建築家は、アートテックではなく本物の木を選ぶだろうからです。一方でアートテックには、どんどんアイデアをアップデートすることで、見たことのないモノをつくり出せる可能性があります。
中井:おっしゃる通りです。最近はアートテックの意匠性もさらに向上しているので、「メンテナンスコストを抑えられるだけでなく、重量も軽いし、その他さまざまなメリットを鑑みると、本物が使えたとしてもアートテックのほうがいいんじゃないか」と採用されるケースも増えてきました。
江川:耐久性の側面でも「アートテックを使って建てられて20年以上経つ物件がすでに存在する」とお話しして、ご安心いただくケースが多いですね。特に大手ゼネコンさんの大きな建物や、公共建築は安全性を重視しますから。
後藤さん:社会の流れとして建築物のメンテナンス性が重視されることも増えています。アートテックはその辺りにも配慮された建材なので、時代にもフィットしていますよね。
——アートテックが大きな可能性を秘めた建材であることが伝わりました。最後に、座談会の感想と、未来のアートテックの活用方法について後藤さんにお聞きしたいのですが。
後藤さん:既製品であるにもかかわらず、そのカスタマイズ性の高さに驚きました。同時に、これを活用する建築家の「構想力」が問われるな……とも感じました。構想力が高ければ高いほど、要件に細かくフィットしたアートテックをつくり出せるからです。
だからこそ、建築家のトレードマークともなるデザインを生み出せる可能性も秘めているように思います。隈研吾さんでいう木製のルーバー、安藤忠雄さんでいうコンクリート打放しのような。建築家がDNPと組んで、そんな独創的なデザインの建材を開発できるようになるとしたら、自身のブランディングにもつながるし、何より建築設計がとても楽しくなりそうですね。
|
後藤連平さん |
※記載された情報は公開日現在のものです。あらかじめご了承ください。
- X(旧Twitter)にポスト(別ウインドウで開く)
- Linkdin
- メール
- URLをコピー
- 印刷