沿革
1876明治9年
秀英
秀英舎創業。数寄屋河岸御門外の弥左衛門町(現 銀座4丁目)
1877明治10年
秀英
『改正西国立志編』完成(日本初の国産活版洋装本)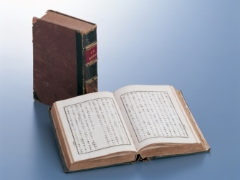
1878明治11年
秀英
舎則を定める。印刷業を「文明ノ営業」と表現
1881明治14年
秀英
活字の自家鋳造を開始
1882明治15年
秀英
製文堂(秀英舎活字販売課)を創設。活字の販売を開始
1886明治19年
秀英
牛込区市谷加賀町に工場を開設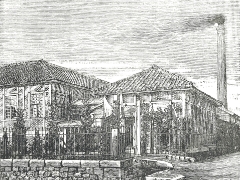
1889明治22年
秀英
佐久間貞一が舎長に就任
1890明治23年
秀英
「国民新聞」の印刷を受託。民友社内に出張工場を設ける
1891明治24年
秀英
佐久間貞一が印刷雑誌社を設立し、『印刷雑誌』を発刊
1894明治27年
秀英
株式会社秀英舎を設立登記
1895明治28年
秀英
本舎工場の増築工事完了。国内初の鉄骨煉瓦造建物
1899明治32年
秀英
凹版で大阪市築港公債証書を印刷
1907明治40年
日清
日清印刷創業。牛込区榎町(現 新宿区榎町)
1910明治43年
秀英
製文堂、『活版見本帖』を発行
1912明治45年
大正元年
秀英
秀英体活字の大改刻が完了
1916大正5年
秀英
市谷工場に四六全判オフセット印刷機を設置(オフセット印刷開始)
1923大正12年
秀英
関東大震災で本店と製文堂が類焼。本店を牛込区市谷加賀町に移転
1924大正13年
秀英
雑誌『キング』(大日本雄弁会講談社)を印刷
1926大正15年
昭和元年
秀英
市谷工場建て替え工事完了。営業所棟竣工
秀英
『現代日本文学全集』(改造社)を印刷(円本ブーム到来)
1927昭和2年
日清
市田オフセット印刷所を吸収合併
秀英
銀座営業所を開設(活字販売所)
1928昭和3年
日清
辻本写真工芸社を買収。原色グラビア印刷開始(日本初)
1932昭和7年
日清
大崎分工場を開設
1935昭和10年
秀英舎と日清印刷が合併、大日本印刷発足。増田義一が取締役社長に就任
1941昭和16年
青木弘、取締役社長に就任
太平洋戦争始まる
1943昭和18年
佐久間長吉郎、取締役社長に就任
1944昭和19年
技術部研究室を設置
1945昭和20年
『日米会話手帳』(科学教材社)を印刷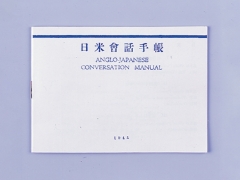
1946昭和21年
4工場が大蔵省管理工場に指定され、日本銀行券の印刷を行う
京都工場を開設
1949昭和24年
東京証券取引所に上場
榎町工場で証券印刷を開始
1950昭和25年
京都工場で紙器印刷を開始
1951昭和26年
「再建5か年計画」を発表、事業領域の拡大を目指す
ビニール、セロハン、布地などへの印刷を始める
大崎工場を紙器専門工場とする
1952昭和27年
日本専売公社からたばこの外函の印刷を受注
多色グラビアエンドレス版の製造に成功。メラミン化粧板(住友ベークライト向け)の印刷開始
1953昭和28年
新東京証券印刷を買収(王子工場の前身)
紀ノ国屋、日本最初のスーパーマーケットを東京・青山に開店
1955昭和30年
北島織衛、取締役社長に就任
『広辞苑』(岩波書店)を印刷(秀英体活字を使用)
1956昭和31年
『週刊新潮』(新潮社)を印刷。出版社による日本初の週刊誌
大阪工場を開設(日本精版を吸収合併)
1957昭和32年
王子工場を開設(軟包装工場)
1958昭和33年
カラーテレビ用部材のシャドウマスクの試作に成功(日本初)
1959昭和34年
『少年マガジン』(講談社)と『少年サンデー』(小学館)を印刷
メサ型トランジスター用蒸着マスクの試作に成功
「チキンラーメン」(日清食品)の袋を印刷
1960昭和35年
埼玉県にエレクトロニクス製品工場を開設
東芝が国産カラーテレビを発表(日本初)。NHKなど5局でカラー放送開始
1961昭和36年
大日本ポリマー(現 DNPテクノパック)を設立。ブローボトル成形開始
中央研究所を設置
鋼板への直接カラー印刷に成功(日本初)
フォトマスク(エマルジョンマスク)を製造
1962昭和37年
メタルプリントを設立(現 DNPエリオ)。富士製鉄(現 日本製鉄)との合弁
紙カップの生産を開始
1963昭和38年
北海道飲料(北海道コカ・コーラ ボトリング)を設立
事業部制を導入
1964昭和39年
香港に大日国際印刷有限公司設立
東京オリンピックの入場券、記念シール、ポスター等を印刷
リードフレームの生産開始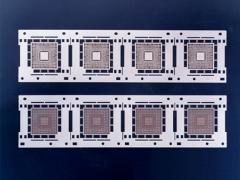
1965昭和40年
グラビア方式の布地印刷技術を開発
ザ・スタンダード・レジスター社と提携、ビジネスフォームの量産開始
1967昭和42年
半導体用フォトマスク(ハードマスク)を製造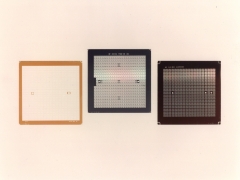
1968昭和43年
横浜工場を開設(紙器工場)
企画制作専門のクリエイティブ・デザインセンターを設置
ニューヨーク駐在員事務所を開設
1969昭和44年
シドニー駐在員事務所とフランクフルト駐在員事務所を開設
四国大日本印刷を設立(現 DNP四国)
ラミネートチューブの生産を開始
1970昭和45年
日本万国博覧会でサウジアラビア館などパビリオン9件の企画設計を担当
西ドイツ・デュッセルドルフにDNPヨーロッパを設立
1972昭和47年
インドネシアに合弁会社ダイニッポン・ギタカルヤ・プリンティング(現 DNPインドネシア)を設立
赤羽工場を開設(二葉印刷を合併)
シーティエス大日本を設立。電算写植システムの実用化を推進
埼玉県に蕨工場を開設
1973昭和48年
埼玉県に狭山工場と鶴瀬工場を開設
奈良工場を開設
磁気プラスチックカードの量産体制を整える
1974昭和49年
DNPアメリカを設立
磁気通帳の本格生産を開始
曲面印刷技術(カールフィット)の技術を導入
1975昭和50年
生産技術研究所(現 生産総合研究所)を設立
レトルトパウチ食品包装技術を確立
木目同調エンボスシートを開発
1976昭和51年
飲料用の液体紙容器(Lカートンシステム)を開発
コーヒークリーム用ポーションパック(雪印乳業)の無菌充填システムを開発
1978昭和53年
大型3次元ホログラムを開発(リップマンホログラムの原型)
1979昭和54年
大阪府に寝屋川工場を開設
北島義俊が取締役社長に、北島織衛が取締役会長に就任
1980昭和55年
バッグインボックス用無菌充填システムを開発
1981昭和56年
「明治ブルガリアヨーグルト」専用容器「MD-1」を開発
全自動フォトマスク製造装置を開発
1982昭和57年
精密電子部品搬送用キャリアテープを開発
PETボトルの生産開始
1983昭和58年
プラスチック成型品への絵付け技術「サーモジェクト」を実用化
埼玉県に久喜工場を開設
書き換え可能なICカードを開発(ICカードの原型)
『広辞苑』第三版(岩波書店)をCTSで制作
リアプロジェクションテレビ用スクリーンの生産を開始
1984昭和59年
転写印刷を応用したレインボーホログラム量産技術を開発
京都市にエレクトロニクス製品の工場を開設
溶融型熱転写記録材の製造技術確立、生産を開始
1985昭和60年
千葉県柏市に研究施設(中央研究所)が完成
日本初のCD-ROM辞書『最新科学技術用語辞典』(三修社)を制作
昇華型感熱記録材の製造技術開発、生産を開始
液晶ディスプレイ用カラーフィルターの生産技術を開発
1986昭和61年
ギンザ・グラフィック・ギャラリー(ggg)を開設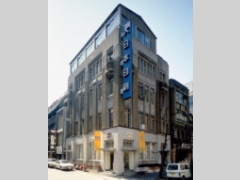
人工関節部材を開発
1987昭和62年
印刷方式の尿検査用試験紙を開発
1989昭和64年
平成元年
岐阜県美術館にハイビジョンギャラリー作品を納入
ICカード事業のスポム・ジャパンを設立(ブル社との合弁)
DNPデンマークを設立。プロジェクションスクリーンの製造販売を行う
1990平成2年
DNPシンガポールを設立
全面圧着はがき「Sメール」を開発
1991平成3年
茨城県につくば総合開発センターを開設
兵庫県に小野工場を開設
岡山工場を開設
1992平成4年
PETボトルのプリフォーム法を開発
1993平成5年
Jリーグ公認データ提供サービスを開始
埼玉県に白岡工場を開設
広島県に三原工場を開設
非接触ICカードを開発
1994平成6年
ダイニッポンIMSアメリカ(現 DNPイメージングコムアメリカ)を設立
公式ホームページ開設
1995平成7年
ベトナム植林事業に出資。新王子製紙(現 王子製紙)・日商岩井(現 双日)と共同
インターネットサービス「Media Galaxy」の運用を開始
京都府に田辺工場を開設(紙器工場)
1996平成8年
建材用EBコート紙の生産を開始
液晶ディスプレイ向け反射防止フィルムの設計技術確立
リチウムイオン電池用電極材の製造技術を開発
福島県に泉崎工場を開設(軟包装工場)
1997平成9年
PETボトルのインライン無菌充填システムを開発
1998平成10年
バリア性に優れた非塩ビ系包材「IBフィルム」を発売
栃木県に宇都宮工場を開設
フルカラーリップマンホログラムの量産技術を開発、「トゥルーイマージュ」製造販売開始
台灣大日本印刷股份有限公司を設立
1999平成11年
茨城県に牛久工場を開設
接触・非接触共用のICカードを開発
半導体パッケージ用超高密度ビルドアップ多層基板を開発
リチウムイオン電池用ソフトパック(バッテリーパウチ)を製品化
2000平成12年
インターネットデータセンターを開設
非接触RFIDタグ「アキュウェイブ」を開発、生産開始
DNPコリアを設立
2001平成13年
カラーフレキシブル有機ELディスプレイを開発
NTTドコモの携帯電話用「FOMAカード」の供給開始
有機ELディスプレイ用蒸着マスク(メタルマスク)を開発
2002平成14年
STマイクロエレクトロニクス社と提携、DNPフォトマスクヨーロッパをイタリアに設立
2003平成15年
銀座に「メゾン・デ・ミュゼ・ド・フランス」を開設(現 メゾン・デ・ミュゼ・デュ・モンド)
太陽電池モジュール部材を開発
2004平成16年
プロジェクター用フロントプロジェクションスクリーンを開発
東京医科歯科大と共同で毛細血管のパターン形成に成功
写真プリント機「PrintRush」の販売開始
2005平成17年
迪文普国際貿易(上海)有限公司を設立
北九州市に黒崎工場を開設
2006平成18年
コニカミノルタホールディングスより証明写真事業等を譲り受ける
神谷ソリューションセンターを開設
ルーヴル美術館との共同プロジェクト「ルーヴル - DNPミュージアムラボ」開始
2007平成19年
宇宙日本食向け包材を開発(日本初)
2008平成20年
オランダにDNP IMSネザーランド(現 DNPイメージングコムヨーロッパ)を設立
財団法人DNP文化振興財団を設立
図書館流通センターと丸善を連結子会社とする
2009平成21年
ジュンク堂書店を連結子会社とする
DICと共同でDICグラフィックスを設立
2010平成22年
CHIグループ(現 丸善CHIホールディングス)を設立。丸善と図書館流通センターが傘下に
インテリジェントウェイブを連結子会社とする
電子書籍と紙の本を販売するハイブリッド書店「honto」を開設
2011平成23年
北九州市に戸畑工場を開設
包装材用バイオマスプラスチックフィルム「バイオマテックPET」を開発
2012平成24年
日本ユニシス(現 BIPROGY)と業務提携
2013平成25年
ベトナム工場を開設(軟包装工場)
DNPファインケミカル宇都宮、稼働開始
ダイニッポン プリンティング タイランド 設立
マレーシアに昇華型熱転写記録材の工場を開設
DNP柏データセンターを開設
2014平成26年
インド駐在員事務所を設置
「DNP京都太秦文化遺産ギャラリー」を開設
「DNP多機能断熱ボックス」を開発
2015平成27年
農業用の反射フィルムを開発
田村プラスチック製品を連結子会社化(DNP田村プラスチック発足)
2016平成28年
フランス国立図書館との共同企画「体感する地球儀・天球儀展」を開催
「サイバーナレッジアカデミー」を開設
市谷に「DNPプラザ」オープン
2017平成29年
日本・デンマーク修好通商航海条約のレプリカを製作
「ミニ腸」の実用化に向けた研究を開始(国立成育医療研究センターと共同)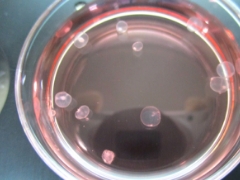
DNP学びのプラットフォーム「リアテンダント」開発
2018平成30年
伸縮自在な薄型スキンディスプレイを開発(東京大学と共同)
北島義斉が取締役社長に、北島義俊が取締役会長に就任
単一素材(モノマテリアル)のフィルムパッケージを開発
2019平成31年
令和元年
電気自動車向けワイヤレス給電用シート型コイルを開発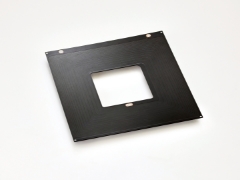
国宝・仁和寺金堂の高精細8K VRコンテンツを制作
情報銀行システムプラットフォームの提供開始(富士通と連携)
2020令和2年
5Gスマートフォン向け薄型放熱部品「ベイパーチャンバー」を開発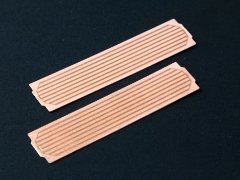
JTBプランニングネットワークを連結子会社化(DNPプランニングネットワーク発足)
DNP超低反射フェイスシールドを開発、販売
2021令和3年
「市谷の杜 本と活字館」オープン
地域共創型空間を開発する「XRコミュニケーション事業」を開始
イリモトメディカルと業務提携
2022令和4年
5G-Sub6周波数帯用フィルム型アンテナを開発
小型照明装置「DNP高視認性パターンライト」販売開始
2023令和5年
半導体パッケージ向け「TGVガラスコア基板」を開発
ナノインプリント製品のファウンドリー事業でSCIVAXと業務提携
シミックホールディングスと事業提携、シミックCMOを連結子会社化
アート画像を提供する「イメージアーカイブ・ラボ」オープン
2024令和6年
「DNP太陽光発電所用反射シート」提供開始
